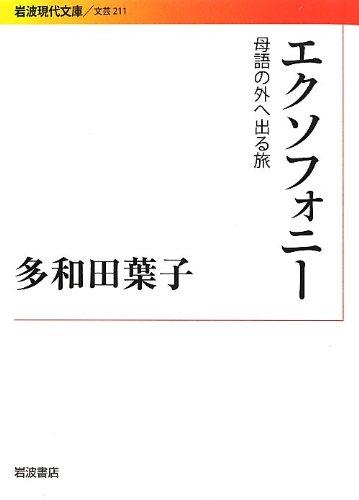岩波現代文庫|2012年10月16日 出版|2021年1月15日 第9刷
部分译文
摘录
P10
ある言語で小説を書くということは、その言語が現在多くの人によって使われている姿をなるべく真似するということではない。同時代の人たちが美しいと信じている姿をなぞってみせるということでもない。むしろ、その言語の中に潜在しながらまだ誰もみたことのない姿を引き出して見せることの方が重要だろう。そのことによって言語表現の可能性と不可能性という問題に迫るためには、母語の外部に出ることが一つの有力な戦略になる。
P31
太平洋を見て感じるのは懐かしさではなかった。むしろ、東京からシベリアを越えてヨーロッパという遠いとこと来てしまったところから更に大西洋を越えて、アメリカ東海岸からアメリカ大陸を横断して、「世界の果て」のカリフォルニアまで来たら、なぜか又、出発点の東京が近くなっていたという不思議さだった。地球はまるというのは、こういうことだったのかとも思う。
P32
昔なら、数年ごとに住む場所を変えるような人間は、「どこにも場所がない」、「どこにも所属しない」、「流れ者」などと言われ、同情を呼び起こした。今の時代は、人間が移動している方が普通になってきた。どこにも居場所がないのではなく、どこへ行っても深く眠れる厚いまぶたと、いろいろな味の分かる舌と、どこへ行っても焦点をあわせられることのできる複眼を持つことの方が大切なのではないか。
P36
言葉そのものよりも、二ヶ国語の間の狭間そのものが大切であるような気がする。わたしはA語でもB語でも書く作家になりたいのではなく、むしろA語とB語の間に、詩的な峡谷を見つけて落ちて行きたいのかもしれない。
P39
わたしは境界を越えたいのではなくて、境界の住人になりたいのだ、とも思った。だから、境界を実感できる躊躇いの瞬間に言葉そのもの以上に何か重要なものを感じる。
P89
母語の外に出ることは、異質の音楽に身を任せることかもしれない。エクソフォニーとは、新しいシンフォニーに耳を傾けることだ。
P99
国民文学と対になった世界文学という概念そのものにはあまり興味は持てなかったが、文学が国境を越える瞬間、言葉が変わることには興味があったので、わたしは、今の時代に「世界文学」というのは翻訳文学のことではないか、というステイトメントを出した。なぜなら、わたしらちは世界の文学に触れるには翻訳文学の世話になるしかない。
P157
人はコミュニケーション出来るようになってしまったら、コミュニケーションばかりしてしまう。それはそれで良いことたが、言語にはもっと不思議な力がある。ひょっとしたら、わたしは本当は、意味というものから解放された言語を求めているのかもしれない。母語の外に出てみたのも、複数文化が重なりあった世界を求め続けるのも、その中で、個々の言語が解体し、意味から解放され、消滅するぎりぎりの状態に行き着きたいと望んでいるからなのかもしれない。
P208
満たされた人生(sinnerfülltes Leben)などという言い方があるが、この場合のSinnはどっちの意味なんだと、わたしなどは意地悪く聞きたくなる。意義ある人生などという立派だが、立派なことをしていても空しい感覚の中に取り残されることはある。Sinnに満たされているということ結局は客観的基準はなく、感覚もいっしょに働いていなければだめなのではないか。
Sinn(意味)は、社会的常識を通して確認するものではなく、自分のSinn(感覚)でとらえるものだと思う。